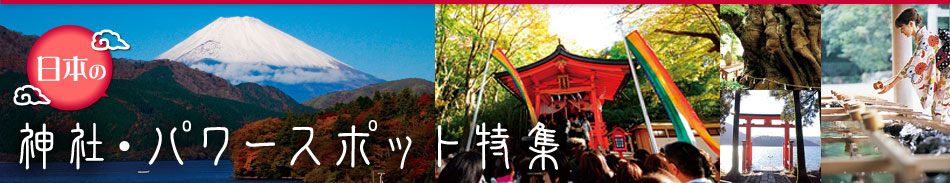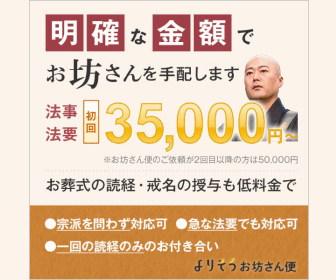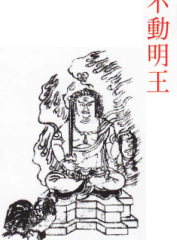戦国武将に人気のあった摩利支天
仏教の中でも身を守ってくれる護身の神として、また
勝利や開運の神として信仰されているのが摩利支天です。
あまり聞いたことがない…
という方もいらっしゃるかと思います。
摩利支天の最大の特徴は
イノシンに乗っているということです。
そのため、目にも止まらない速さで動き回るという
ことから、相手に射止められにくい…
つまり戦いの場で、その速さが最大の防御になっている
ということから護身の神と崇められているのです。
そのため、今ではあまり馴染みがない摩利支天ですが、
江戸時代には弁財天や大黒天とともに信仰されていた
神であり、とりわけ亥年には守り神として、
手厚く信仰されており、また戦国武将に人気があったのです。
現在、摩利支天を祭っている場所として有名なのが、京都市右京区にある聖沢院です。
ここにある摩利支天像は国の重要文化財にも指定されています。
また、東京都台東区にある下町の台所でもある上野アメ横の中にある徳大寺は
日本三大摩利支天とされている日蓮宗の寺院です。
戦国武将に人気の代表的軍神
| 戦国武将に人気の代表的軍神 9万8000いるとされていた軍神だが、 特に多くの武将に信仰された軍神について取り上げてみよう。 |
||
|---|---|---|
 |
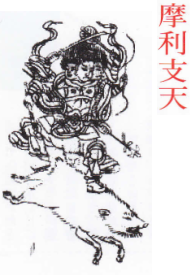 |
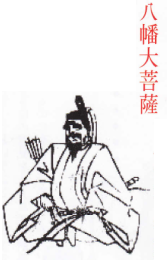 |
| もともとはインドの神クベーラ とされ、多聞天とも呼ばれる。帝釈天に仕える四天王の一尊として、守護神、武神とされている。日本以外のアジアの広い範囲で信仰されている。 |
もともとはインドの神マリシ。 陽炎を神格化したものとされ、実体がないので傷つくこともなければ、逮らえられることもないとされ、その特性から軍神として信仰を集めた |
日本独自の軍神。 ハ幡神を祀る社は日本一の数ともいわれる。神仏習合により仏教と融合 し、ハ幡大菩薩と呼ばれるように。源氏の氏 神でもあり、多くの武将に崇敬されてきた。 |
 |
 |
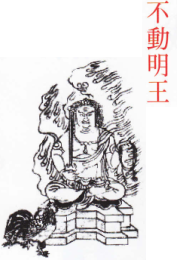 |
| 鎌倉時代以降、武土たちが信仰した軍馬にま たがった地蔵菩薩。戦が困難に陥ったときに 地蔵に祈ったところ勝利に導いてくれ、身代 わりに矢をうけてくれたというエピソードも。 |
北極星、北斗七星を神格化して生まれたもの。妙見とは優れた視力、という意味。北斗七星のうちのひとつの星、破軍星は戦の行方を決めるものとして、武士の信仰を集めた。 | 大日如来の化身とされ、煩悩を抱えるすべての人を紋うため、その覚悟から憤怒の姿をしている。お不動さんの名で親しまれ、特に日本での根強い信仰がある。 |