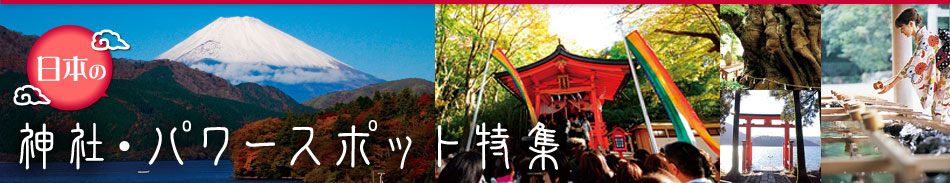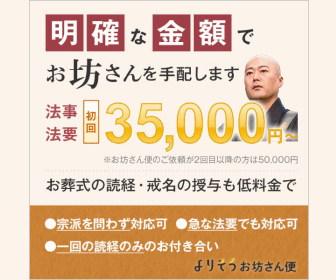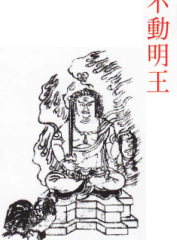戦国武将に人気のあった毘沙門天
現代でも人々の心のよりどころとして、
平安や幸福を招くものとして信仰されているのが七福神です。
七福神には弁財天や大黒天などが
ありますが、その中の一つに毘沙門天があります。
毘沙門天は仏教を信仰する人々を守る
四天王の一人とされています。
そもそもその由来はインドにあり、当地では四方を守る
神として、東の持国天、西の広目天、南の増長天があり、
毘沙門天は北を守る神とされていました。
つまり、これら東西南北を守る神が四天王であり、
毘沙門天はその一つに位置付けられていたのです。
毘沙門天は怒りに満ちあふれた表情をしています。
左手には宝塔、右手には金剛神を握り締めて、邪鬼を踏み付けているのが一般的な姿です。
つまり、これが戦いに挑む際に勝利をもたらしてくれる神だということとなり、
古くから戦国武将の信仰を集めることになったのです。
毘沙門天は京都にある鞍馬寺を始め、
信貴山千手院や山科毘沙門堂、本山寺などで祭られています。
戦国武将に人気の代表的軍神
| 戦国武将に人気の代表的軍神 9万8000いるとされていた軍神だが、 特に多くの武将に信仰された軍神について取り上げてみよう。 |
||
|---|---|---|
 |
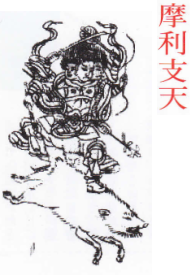 |
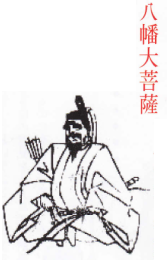 |
| もともとはインドの神クベーラ とされ、多聞天とも呼ばれる。帝釈天に仕える四天王の一尊として、守護神、武神とされている。日本以外のアジアの広い範囲で信仰されている。 |
もともとはインドの神マリシ。 陽炎を神格化したものとされ、実体がないので傷つくこともなければ、逮らえられることもないとされ、その特性から軍神として信仰を集めた |
日本独自の軍神。 ハ幡神を祀る社は日本一の数ともいわれる。神仏習合により仏教と融合 し、ハ幡大菩薩と呼ばれるように。源氏の氏 神でもあり、多くの武将に崇敬されてきた。 |
 |
 |
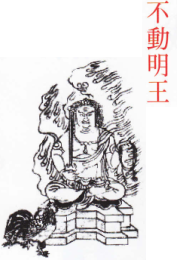 |
| 鎌倉時代以降、武土たちが信仰した軍馬にま たがった地蔵菩薩。戦が困難に陥ったときに 地蔵に祈ったところ勝利に導いてくれ、身代 わりに矢をうけてくれたというエピソードも。 |
北極星、北斗七星を神格化して生まれたもの。妙見とは優れた視力、という意味。北斗七星のうちのひとつの星、破軍星は戦の行方を決めるものとして、武士の信仰を集めた。 | 大日如来の化身とされ、煩悩を抱えるすべての人を紋うため、その覚悟から憤怒の姿をしている。お不動さんの名で親しまれ、特に日本での根強い信仰がある。 |