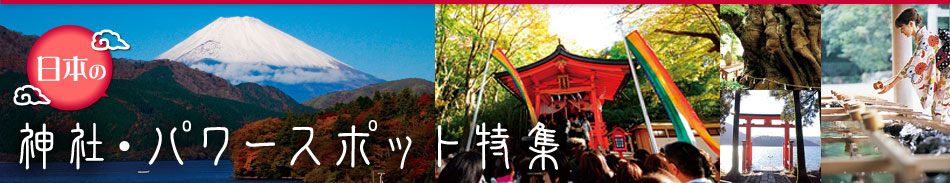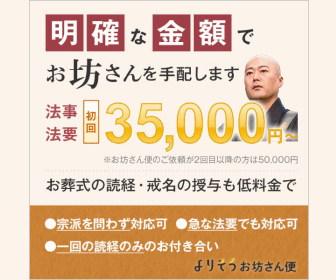神道と稲作には密接な関係がある
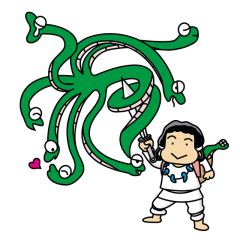 日本人が日頃の食生活を送る上で絶対不可欠の食材といえば、やはり米でしょう。
日本人が日頃の食生活を送る上で絶対不可欠の食材といえば、やはり米でしょう。
これは現代においても、太古の昔においても同じことが言えますが、米は日本人が生活を営む上では大切な役割を担っているために、毎年の稲作の成否は生活にも大きな影響を与えるのです。
だからこそ、昔から人々は稲作の成功、つまり五穀豊穣を神に祈るとともに、稲を収穫した際には神に感謝してきたのです。
そのため、稲作と神道は太古の昔から切っても切り離せない関係にあると言えます。
神道には稲の収穫を感謝する祭りとして新嘗祭を行ってきました。
新嘗祭は昔は11月の第二の卯の日、
今では11月23日に日本各地の神社で行われています。
まず、稲作のスタートとなる春先に祈念祭と呼ばれる五穀豊穣の祈願を行いますが、
無事に稲が収穫出来たら、新嘗祭としてその稲を神前に奉納するのです。
神様に感謝し、もてなすというのがまさに「新嘗」の意味するところであり、
このようにして神道は稲作と密着していったのです。